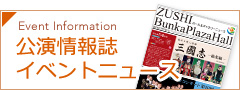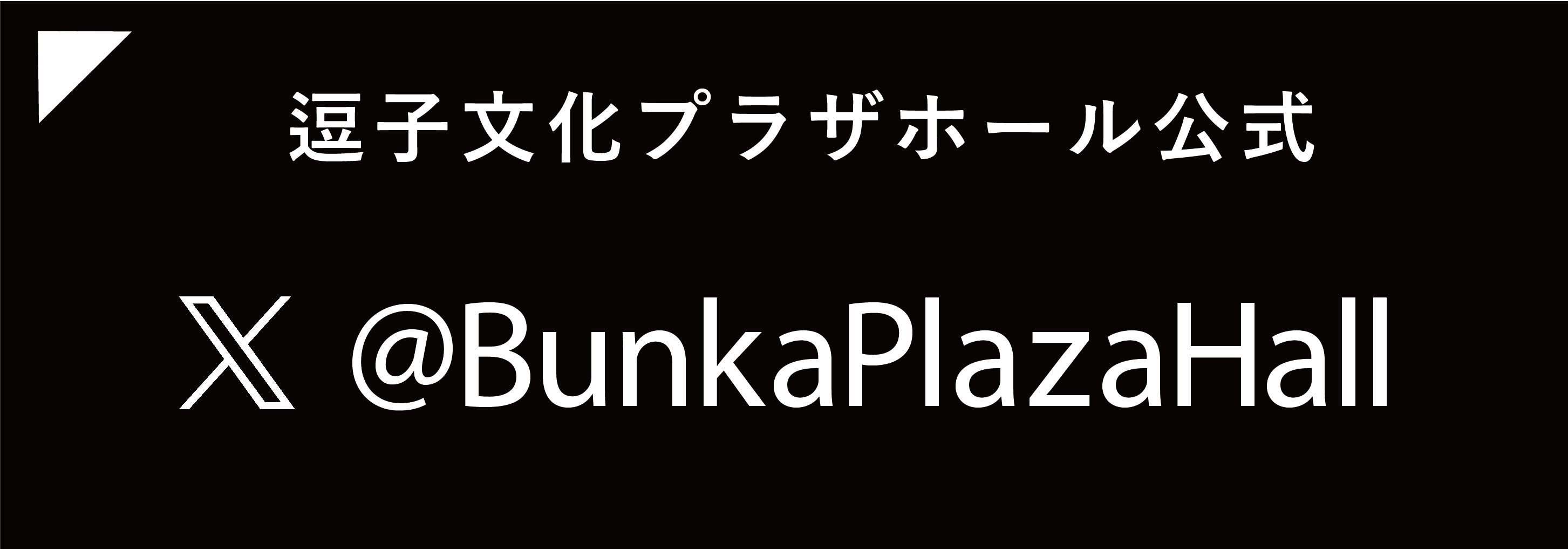ホール主催の催しの感想や雰囲気をみなさまに発信する活動をしている“情報発信ボランティアライター”の方によるレポートをお届けいたします。
********************************************
プログラムを見ると、全10曲のうち大半がクラシック。奥村愛氏の意気込みと自信がうかがえる。
開演時間と同時にピンクをメインとしたドレス姿の奥村氏と白いドレスの酒井有彩氏(ピアノ)が颯爽と登場し、すぐに演奏が始まった。氏のヴァイオリンにはテクニックにごまかしがない。丁寧で誠実に弾いていくところに好感をもった。表現も同様で、音色にはツヤがある。氏の魅力の1つは、小品を心地良く弾きこなすところではないだろうか。長く愛され続けている『愛の挨拶』(E.エルガー)、優雅で優しい曲を繊細に表現。『シンコペーション』(F.クライスラー)では、見事な弓さばきで音に豊かな表情をつけ、リズミカルなピアノともピタリと合って爽快。ツヤのある音色で伸びやかに弾いた『メロディ』(P.チャイコフスキー)。音色、表現、テクニック・・・すべてが揃ってきれいに弾きこなした『序奏とロンド・カプリチオーソ』(C.サン=サーンス)は、氏に合った選曲だと感じた。印象的だったのは、映画『ラヴェンダーの咲く庭で』の同名テーマ音楽(N.ヘス/加藤昌則)。あの心温まる名画の世界に引き込むようなヴァイオリンとピアノ。名シーンの数々が心に浮かぶ。喜びも切なさも深く表現されていて秀逸だった。
後半からはヴァイオリンの前田尚徳氏も加わり、ヴァイオリン二重奏+ピアノ。ツヤのある音を響かせる2台のヴァイオリンに流れるようなピアノ。3台の楽器が見事に融合し、美しい旋律に抑揚と強弱をつけて聴き応えがあった。中でも『ナヴァラ』(P.サラサーテ)は、明るいメロディにスピーディかつエレガントな演奏で、思わず踊り出したくなるような楽しさがあって心が弾んだ。
奥村氏、酒井氏、前田氏はこの日の午前中に同ホールで1つのコンサートをこなしてからの2時間に渡る本公演だった。奥村氏曰く「ハードなスケジュール」だったが、疲れを感じさせず、最後まで良い演奏を届けてくれた。
猛暑の夏の昼下がり。流れ来る音楽に清涼感を感じ、涼んだ気分でホールをあとにした。
ボランティアライター 青栁有美
********************************************
世界には「美しい」や「愛」という言葉があふれているが、具体的にどのようなものかをきちんと説明や表現できる人はほとんどいないのではないだろうか。だが、それらを頭で考えず心で感じる瞬間が人生にはあるにちがいない。そしてその答えを私は、逗子文化プラザなぎさホールで体感した。夏の午後、同ホールで、奥村愛さんによるヴァイオリンリサイタルで。
ステージ中央に立つ彼女は、その姿も美しいが、なによりも奏でる音楽にこそ「美しさ」や「愛」が凝縮されているようだ。E.エルガー作曲『愛の挨拶』で幕を開けたこの日のリサイタルは、選曲からして観客の心を優しく包みこんでくるようで、曲名通りの愛らしさと親しみやすさに、初めて聴く人もどこか懐かしい温もりを感じたことだろう。私自身もまるで奏者から「愛のメッセージ」を受けているような錯覚を覚えたほどだ。
F.クライスラー作曲『シンコペーショ』や『愛の喜び』などでは、華麗で情熱的な技巧を惜しみなく披露し、繊細さと大胆さを自在に行き来するなかで、緊張感をはらんだ音質と、その合間に訪れる柔らかな旋律との対比がなぎさホールに流れる空気を震わせ、観客の心を揺さぶっているようだ。
音楽の持つ力とは。例えば「愛」。恋人たちがどれだけ言葉を尽しても伝わらないか、錯覚している感情。当日の演奏は、その答えの本質に迫っているようだった。錯覚や誤解などを超えた「愛」というものの真実の姿を表現しているようだと感じた。また彼女の演奏にはどこか慈愛のようなものが漂っている気がする。テクニックや表現力の高さもちろんだが、それ以上に音楽に寄せる真摯な思いが感じられる。その思いは共演者の酒井有彩さん(ピアノ)、前田尚徳さん(ヴァイオリン)にも自然に伝わり、3人のアンサンブルは素敵な絵画のようだった。
演奏の合間に客席を見渡すと、幅広い世代の人たちが、息をのんで演奏に耳をかたむけていた。同日午前中には奥村さんを中心に「0歳からのコンサート」も開催されたそうだ。鑑賞した幼い子どもたちにとっても、奥村さんの音楽は生涯忘れられない貴重な体験になったことだろう。
プログラム後半では、D.ショスタコーヴィッチの『5つの小品』などを通して、多彩な表情を見せてくれた。軽やかで洒落た雰囲気、時に陰影を帯びた深みのある響き。それらを聴くうちに「美しさ」とは単に形や音の流れだけではなく、そこに潜む感情や人生の機微を含めて輝きを増すのだろうと気づかされた。
アンコールは、山口景子・編曲「日本の四季メドレー」。私にとってはメドレーの中の一曲『ふるさと』の演奏から、今から80年前の8月に戦争が終わったことを想起した。そしていま現在平和な時を過ごせることに思いを致し、リサイタルでヴァイオリンが奏でた残響とともにホールをあとにした。
ボランティアライター 海原弘之
*******************************************
今年はいつにもまして暑い日が続く。出かける気力が萎える中、行ってしまえば涼しいホールで音楽を楽しむのは一興だ。しかし、すでに奥村氏は、朝一番でファミリー向けコンサートを行ったばかりだった。元気だなあ。1738年製のカミロ・カミリという楽器、無教養な私は初めて聞くので、どんな音がするのかわくわくする。一等席で開演を待つ。
定刻に登場したのはピンクのドレスに身を包んだ奥村氏、そして純白のドレスのピアニスト酒井氏。二人とも若さにあふれ清々しい。早速の一曲目「愛の挨拶」の一音目から、あ、なんだろう、と音に惹きつけられる。クラシックのヴァイオリンのイメージは、澄み切った鋭い音と思っていたが、この音はなんだか微かな二重音が聞こえる気がする。ちょうど、ジブシー・ヴァイオリンとか、アイリッシュ・ヴァイオリン(フィドル)のような、哀愁漂う、いうなればモンゴルの喉歌(のどうた)のような音が聴こえる気がした。
予期しなかった音に集中力が高まる。奥村氏、淡々と曲紹介をしながら気負うこともなく演奏を続ける。ピアノとのコンビネーションが、まるでシンクロナイズドスイミングのようにぴったりと、まさしく「息があって」いて、聴いているうちにどちらが主だかわからなくなってくる。奥村氏は大きく息を吸って、ピアニストに弾き出しの合図をし、おもむろに音楽が流れ出す。やはり、基本は歌なんだと思う。様々な難しい技巧があることなど一切感じさせない、そのことを忘れるほどに滑らかな、水の流れのような音楽がホールを包む。ピアノがまた素晴らしい。どちらも主役、多声音楽のようだ。ヴァイオリン、四曲目で、音が変わって、澄み切ったクラシックの音になる。変幻自在で、それでいて最後にわざと、まるでジャズを彷彿とさせるような嗄れ声を出して見せる。なんだか、すごい!
それは第二部の二重奏になっても続き、相変わらず淡々と、聴衆に一切緊張感を与えず、同時に集中させる、心地よい流れに包まれるような演奏が続く。どの楽器も互いの音を圧倒して支配することがない。どの音にも聞き惚れる。これが奥村氏の真髄なのだろう。まるで見事な共時性で泳ぐイルカの群れの歌を聞いたような、さわやかで、素敵なひと時だった。最高の納涼に、感謝!
ボランティアライター 不破理江
********************************************
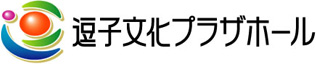
_ライター青柳様-scaled.jpg)
_ライター海原様-scaled.jpg)
_ライター不破様-scaled.jpg)